CARBON JUNCTION vol.3
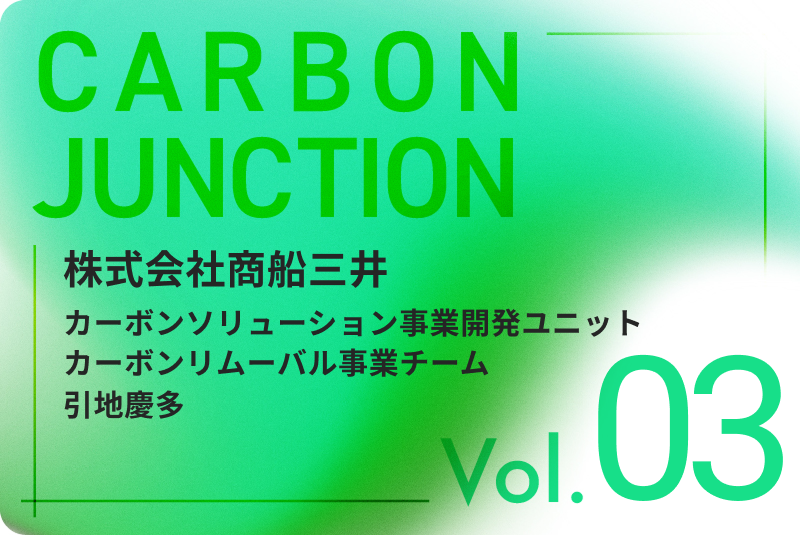
思い返すと中学生のころ「気になる新聞記事について調べる」という宿題で、海面上昇で沈むツバルと京都議定書の排出権取引の記事を選んだことが、この分野との初めの接点だったと思う。子どものころから生きものが好きで、環境というテーマに興味を持ち続けてきた。
大学受験を機に改めて何に興味があるか考えた際に、環境だ!と思い「環境」とつく理工系の学科に入学。ちょうど入学した年には、生物多様性条約のCOP10が愛知であって、学生団体のメンバーとしてサイドイベントに参加するなど、環境について色々な視点から関わる機会に恵まれた。その中で、学科で学ぶ資源関連中心の環境よりも、生きものに関わる自然環境に、より興味があると再認識し、2年生に上がるタイミングで人間科学部に転部した。これが大きな転機だった。
「環境問題を解決するには、地域の貧困も解決しないと、持続的な解決にはならない」 ──教授の話に衝撃を受け、その研究室に入ることを決めた。
そこで学んだのが、開発援助とカーボンクレジットだった。修士までその研究室で勉強させてもらい、VCSのメソドロジーや、アマルティア・センの「不平等の再検討」を教材として、カーボンクレジットの基礎や、地域間・世代間の公平性について学んだ。特にインドネシア西カリマンタンにあるREDD+プロジェクトのサイトで修士論文を書けたことは、貴重な経験として今の糧となっている。現地ではホームステイをさせてもらいながら、森林のプロット調査と住民へのインタビューを行った。地域の方と同じ生活をする中で、集落によっては山からの水を飲み、他の集落では雨水をそのまま飲んだ。飲み水の確保ひとつとっても、集落ごとに森からの恩恵の感じかたが違うなど、実体験として多くの気づきを得ることができた。
就職活動をする中でも環境に携わりたいという思いは消えず、1社目の国際航業では衛星画像を中心としたリモートセンシング技術者として、森林に限らず様々な分野で経験を積んだ。2020年代に入ってからは、能動と受動の両面で民間企業のサステナビリティへの関心が高まり、その影響力の大きさに可能性を感じ日本総合研究所に転職をした。現在はこれらの経験を持って、商船三井でカーボンクレジットに携わることができている。社内で議論をし、プロジェクト現場で植林した樹木の成長を直に確認できることにやりがいを感じている(現場は水道がなくシャワーも雨水を浴びるのだが、これも学生時代の経験からかすぐに順応できた)。
パリ協定6条の運用が合意され、さらに注目を集めるカーボンクレジット。その根本には京都議定書で、1992年の地球サミットにおけるリオ宣言にて明文化された「共通だが差異ある責任」の考えに基づき、導入された経緯がある。将来世代のためにも、このことを忘れずに日々の業務に臨みたい。私はカーボンクレジットが環境問題の解決、地域住民の生活改善、そして企業価値の向上に資するものになり得ると期待している。しかし、こうした取り組みには複数のカウンターパートを必要とすることが多く、一筋縄ではいかないこともまた事実である。だからこそ私一人では微力ながらも、多くの方と協力して一緒に取り組むことで、環境と経済の両立に貢献していきたい。

“学生時代に行った、インドネシア西カリマンタンにあるREDD+プロジェクトのサイトで森林の調査中の様子”





