CARBON JUNCTION vol.6
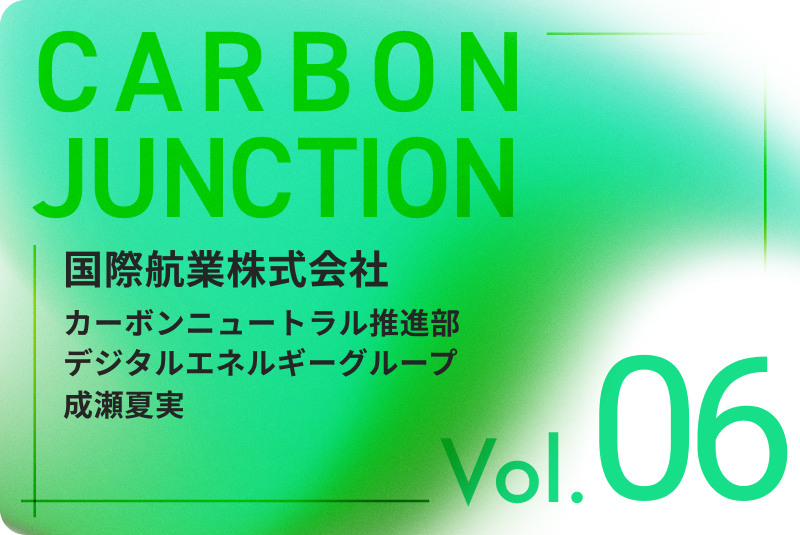
「縁側」という一見ニッチなテーマが、私のキャリアの出発点だった。2013年に大田区の町工場に就職し、会社員の傍らで立ち上げたのが「縁側なび」というWEBメディアだった。全国の縁側を訪ね歩き、記事にまとめて公開する活動は思いのほか反響を呼び、寄稿記事がバズを起こすこともあった。決して大規模なメディアではなかったが、NHKの「美の壺」や新聞、ラジオに紹介いただく機会もあり、縁側というテーマが想像以上に多くの人に届いていることを実感する日々だった。2014年には独立し、フリーランスのWEBライターとして活動を本格化。10年間で240件を超える縁側を取材しながら、企業のオウンドメディア運営や記事執筆も手がけていた。

“お気に入りの我が家の縁側”
芽生えてきた「サステナブルな暮らし」への関心 ――高気密高断熱住宅を自ら建築した
そんな日々の中で芽生えてきたのが「サステナブルな暮らし」への関心だった。2019年頃から省エネや環境分野に目を向け、2020年には高気密高断熱住宅を自ら建築した。もちろん縁側付きの家だ。最初は性能よりデザインを重視したいと思っていたが、住んでみると、もうこの快適さを手放すことはできなかった。夏も冬も家の中は25度前後で安定し、湿度は60%を維持。真冬でも半袖で過ごせるほどで、特にお風呂上がりに感じていた寒暖差のつらさがなくなったことは大きい。一軒家は寒いという思い込みが消え、快適な住環境に守られるようになって、日々の生活の質が格段に上がった。光熱費も1万5000円程度と、以前の家に比べて半分ほどに抑えられている。冬の朝も寒くて布団から出られないということがなく、毛布すらいらなくなった。
そんな暮らしをしていると、自然と他の選択も変わってきた。家庭で出る生ごみは「キエーロ」と呼ばれるコンポストで処理し、ガソリン車からEVに切り替えた。できることから一歩ずつ減らしていく実感があり、それが小さな自信につながっている。省エネ住宅に住んでいるという実体験は、持続可能な社会づくりに対する姿勢を自分の中でより強いものにしてくれた。
2024年に国際航業へ入社してからは、これまでの経験を背景に、脱炭素に関わる新たな仕事に取り組んでいる。縁側なびを通じて「人が集まる場の価値」を見てきた私にとって、環境のテーマも結局は「人と人をつなぐ場づくり」とつながっているように思う。住まいやライフスタイルから始まった小さな実践が、社会や事業につながり、そしてまた人とのつながりを生んでいく――その循環の中に身を置いていることが今は嬉しい。
「縁側」という温かな場から始まった私の道は、いま「エネルギーの縁側」とも呼べる場所へとつながっているのかもしれない。これからも、自分の体験を軸に、誰かの暮らしや選択に寄り添えるような形で、脱炭素社会への橋渡し役を果たしていきたいと思っている。





