CARBON JUNCTION vol.5
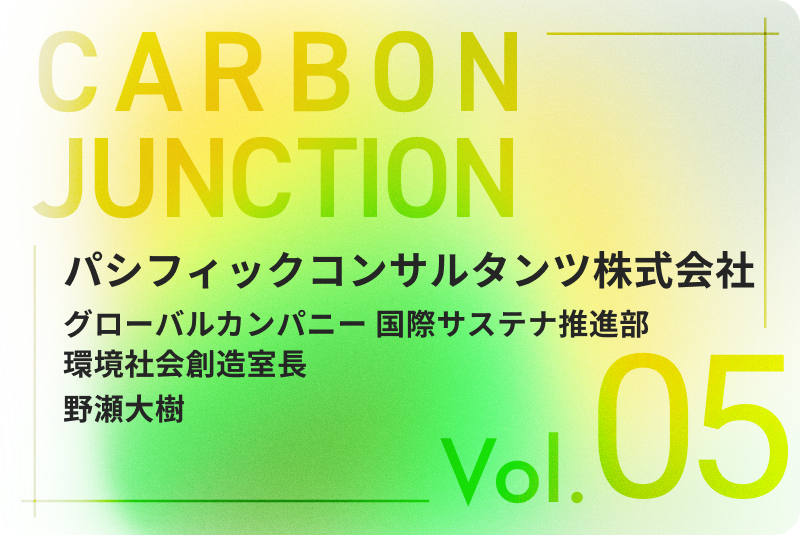
中学生の頃からアイルトンセナや中嶋悟が活躍していたF-1が好きで、漠然と将来は自動車関連の仕事につきたいと思っていた。そのため大学・大学院では機械工学を専攻し、運よく2002年にスズキに入ることができた。スズキは軽自動車が有名だが、配属先ではインドネシアで生産して世界各地にも輸出する自動車のエンジン周り部品の設計に従事した。今でも仕事で訪れる国によっては、自分が設計に関わったバンが元気に走っているのを見ると少し感慨深い。

“サンパウロにあるアイルトンセナのお墓にお参り”
一方で、海外向け自動車の設計に携わったことが、私に環境面での途上国開発支援に関心を持たせるきっかけともなった。開発途上国では経済発展と共に自動車保有台数の爆発的な増加とCO2排出を含む環境への大きな負荷が予想され、私の関心は「開発途上国の経済発展と環境課題の解決との両立のあり方」に次第に移っていった。思い返すと、入社面接で「ルーフでの太陽光発電や排気熱を活用した熱電発電で電力を供給可能な小型自動車を開発したい」と話した記憶があり、今の関心が根底にはあったのかもしれない。
「やらずに後悔するよりやって後悔する方が良い」――英国イーストアングリア大学大学院環境科学専攻へ
30歳前であったので「やらずに後悔するよりやって後悔する方が良い」と思い立ち、2008年、途上国開発と気候変動対策について環境経済やサステナビリティの観点などから多角的に学ぶことができる英国イーストアングリア大学大学院環境科学専攻に進んだ。当時インドタタ自動車が低価格で販売した自動車のナノ(10万ルピー程度)が普及した場合のインドのGHG排出量への影響について修論をまとめて何とか修了することができた。余談だが、修了した2009年は「クライメートゲート事件」が起こった年であり、イーストアングリア気候研究ユニットが時折ニュースを賑わしていたのを覚えている。
リーマンショックやら何やらのため日本に帰国してからは、日本国内で複数の気候変動関連NGOでアルバイトし、日本の気候変動政策調査や議員会館での報告会の手伝いなどをしていた。これは市民社会目線で気候変動問題をとらえる良い勉強になったと今でも思っている。同時に、偶然に偶然が重なりパシフィックコンサルタンツ地球環境研究所(当時)でもアルバイトを掛け持ちすることになり、これが、私がコンサルタントを仕事として本格的に国内外の気候変動対策に関わっていくこととなった開始点である。なお、後に知ったが、イーストアングリア在学中に当社の地球環境研究所長(当時)が同大学にコンサルタント業務の説明に来られていたが(私も説明会には参加していた)、当時は国際機関や国際NGOに関心がありコンサルタントを仕事にすることに関心が無かったため残念ながらあまり覚えていない(しかし、不思議な縁は感じる)。
同研究所はリオサミット以前から国内外の気候変動問題をフォローするなどしており、途上国開発と気候変動対策の両面に携わりたいと思っていた私には最適な環境と感じたため2010年11月に入社を決めた。なお、当社での最初の仕事はベトナムでの2輪車の燃費改善事業のCDM化実現可能性調査であった。以降、かれこれ15年、CDM、JCMなどのカーボンクレジットや国内外適応政策支援などに関わり、途中2年間は環境省に出向しつつ、現在もJCM事業開発支援や開発途上国の気候変動対策支援に携わっている。
気候変動は刻一刻とタイムリミットが近づいてきているが、世界の気候変動対策と途上国開発に日本企業の技術やノウハウを活用できるカーボンクレジット制度の活用について、微力ながら今後も貢献していきたいと思う。
パシフィックコンサルタンツの取り組み
・カーボンクレジット関連問い合わせ先:JCM_pckk@tk.





